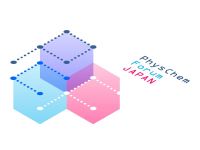NaCl共存下におけるトスフロキサシントシル酸塩の溶出試験:ヘミ塩酸塩の粒子表面析出
2025-08-12
トスフロキサシントシル酸塩(TFLX TS)は、溶出性が低く、経口吸収率も低い薬物です。
以前の研究で、生理学的炭酸緩衝液(pH6.8, 10 mM BCB, I = 0.14 M (NaCl))とJP2において、溶出プロファイルが大きく異なることを見出していました。
そこで今回は、TFLX TSの溶出試験について、詳細に検討しました。
トスフロキサシンはpKa = 5.8 (A), 8.7 (B)であり、pH 6.5の水中では、主にzwitterion型(z = -+0)として存在します。
Okamoto, N., Yamamoto, H. & Sugano, K. Dissolution Profile of Tosufloxacin Tosylate in Biorelevant Bicarbonate Buffer Containing Sodium Chloride: Precipitation of Hemi-hydrochloride Salt at the Particle Surface. Pharm Res (2025). https://doi.org/10.1007/s11095-025-03905-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s11095-025-03905-4?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20250811&utm_content=10.1007%2Fs11095-025-03905-4
(オープンアクセスです)
まずはじめに、pH6.5, 10 mM BCB, I = 0.14 M (NaCl) (BCB-NaCl)における残存粒子をPXRDとDSCで分析しました。
すると、残存粒子は、従来知られていたトスフロキサシンフリー体2水和物(TFLX FF)とは一致しませんでした。
溶出試験液の組成を変えて残存粒子を測定すると、NaClを含まない場合は、TFLX FFが析出してくることが分かりました。
したがって、BCB-NaClで発見された新規結晶は、NaClが原因で生成されることが分かりました。
ここまでは、すんなりと研究は進みした。
しかし、この残存粒子は何なのか?
そこで、標準物質の別途合成に取り掛かりました。
まずは、TFLX TSの再結晶から始めました。(残存粒子が不純物の可能性もありますよね?)TFLX TSは、水だけでなく様々な溶媒に難溶でしたが、エタノール/水混液を用いた温度差法で、きれいに再結晶できました。(Figure 1)
次に、TFLX FFを作成しました。まず初めに、TFLX TSをエタノール/水混液加熱して溶かします。次に、中和等量のNaOHを加えると、TFLX FFがさっと析出します。
実は、このTFLX FFは、100%RHのチャンバーから取り出した直後は、約4水和物になっています(TG-DTA)。しかし、室内条件では速やかに2水和物になります。
したがって、水中では4水和物の可能性が高いです。
最後に、TFLX FFからTFLX塩酸塩を作成しました。TFLX FFも水だけでなく様々な溶媒に難溶でしたが、NaOH溶液には溶けます。
そこでまず、TFLX FFをNaOH溶液で完全に溶かします。
次に、1:1等量の塩酸を一気に加えます(NaOHのモル量を引いた後)。すると、結晶がさっと析出します。
PXRDからは、TFLX FFの残存は否定されました。したがって、塩酸塩結晶が析出したことになります。
この塩酸塩結晶も、水中では10水和物ですが、室内条件では速やかに0.5水和物になります。(これらの等量は化学量論比が分かった後に再計算したものです。)
この結晶のPXRDとDSCは、BCB-NaClにおける残存粒子と一致しました。
したがって、BCB-NaCl中では、pH 6.5であるにもかかわらず、塩酸塩結晶が析出しています。
電子顕微鏡などでの結果から、これは粒子表面析出であることがわかりました。
残る問題は、この塩酸塩結晶の化学量論比の同定です。
この時点で、我々は、TFLXの化学構造から、この塩酸塩結晶は、TFLX:HCl=1:1ではないかと考えていました。
理想は、単結晶構造解析ですが、塩酸塩結晶は調べた範囲では、すべての溶媒に不溶で、再結晶で大きな結晶を作ることはできませんでした。
また、水和数が不安定であるため元素分析も諦めました。
そこで、pH溶解度プロファイルを測定しました。pHはHClで調整しました。
すると、これまで全く見たことが無い、pH溶解度プロファイルが得られました。(Figure 7B)
このpH溶解度プロファイルは、1:1あるいは1:2では、全く説明できませんでした (TFLXは低い塩基性pKaを持っているので、低pH側では1:2の可能性もありました)。
ここで、我々の研究は、座礁に乗り上げてしまいました。
pH溶解度プロファイルを取り直したり、別途合成を繰り返したり、TFLXとH2Oの精密定量を試みたり(水和数が不安定で難しい)、、、いろいろしました。
もちろん、pH滴定も考えました。通常、pH滴定は溶液状態で行います。
しかし、上述のように、この塩酸塩結晶は溶媒に不溶です。
固体懸濁液では、平衡になるまでの時間がかかるのでpH滴定は大変なのです。
でも、最後の手段として、固体懸濁状態でのpH滴定を、学生にやってみてもらいました。
結果は、TFLXとHClの比は2:1であることを示していました。(Figure S3)
(対照として、TFLX TSのpH滴定もおこない、こちらは1:1となりました。)
これは、にわかには信じられない結果です。
この化学量論比(2:1)(Hemi)は、硫酸、フマル酸や、マレイン酸のように2価以上のカウンターイオンの場合はよく知られています。しかし、1価の塩酸でこのような化学量論比は、通常考えにくいのです。
そこで、TFLX:HCl=2:1の場合のpH溶解度プロファイルの理論式を考えてみました。
この化学量論比の場合、溶解度積は、Ksp = [TFLXH+][TFLX][Cl-]となります。
これを電荷中性の式に入れて解くことで、pH溶解度プロファイルが得られます(3次方程式なので、2分法で解いています)。
すると、pH溶解度プロファイルの実験データと完璧に一致しました。
さらに、念のため、本分野の大家であるAlex Avdeefさんにデータを送って、解析してもらったところ、TFLX:HCl=2:1で間違いないということでした。
Alex Avdeefさんも、「このようなpH溶解度プロファイルは初めて見た」と言っていました。
さて、ここまで来て、もう一度溶出試験の結果を見直してみました。
TFLX TSが解けてTFLX FFが固体として析出する場合、溶液中にトシル酸(R-SO3H)が放出されますので、緩衝能が低い溶液中では、溶出試験後のpHが下がります。
これは、実際にそうなります。(Table II)
一方、TFLX TSが解けてTFLX HCl(1:1)がとして析出する場合、トシル酸(R-SO3H)が放出されますが、同時にHClが取り込まれますので、溶出試験後のpHはそのままのはずです。
しかし、Table IIをよーーーく見てみると、塩酸塩結晶が析出している場合でも、溶出試験後のpHはやや下がっています。
これはなぜか???
Ksp = [TFLXH+][TFLX][Cl-]が析出する場合は、トシル酸が2分子放出され、塩酸が1分子取り込まれますので、差し引き1分子の酸が放出されます。
pHはこのことを教えてくれていたのです。
その後、他の薬物でヘミ塩酸塩がないかを文献検索したところ、2つだけ事例がありました。pH溶解度プロファイルは、今回の結果が初めての報告だと思います。
今回の結果は、非常に稀なケースと思われます。
In vivo予測の観点からは、これまで単にイオン強度や浸透圧の調整程度に考えられていたNaClが、実はこんなことを引き起こすことがあるというのが面白い点です。
これは、pH 6.5で起きています。塩酸酸性の低pH側では塩酸塩が析出する事例は多数ありますが、pH 6.5でこのような現象が起きることは、想定外でした。
製薬メーカの分析力であれば、最初の段階で組成を決定できたのかもしれません。しかし、残念ながら大学にはそのような装置はありません。
しかし結果として、ヘミ塩酸塩の驚くべき挙動に気付くことができたと思います。
[TFLXH+][TFLX][Cl-]は、塩なのか?共結晶なのか?面白いですね。
以前の研究で、生理学的炭酸緩衝液(pH6.8, 10 mM BCB, I = 0.14 M (NaCl))とJP2において、溶出プロファイルが大きく異なることを見出していました。
そこで今回は、TFLX TSの溶出試験について、詳細に検討しました。
トスフロキサシンはpKa = 5.8 (A), 8.7 (B)であり、pH 6.5の水中では、主にzwitterion型(z = -+0)として存在します。
Okamoto, N., Yamamoto, H. & Sugano, K. Dissolution Profile of Tosufloxacin Tosylate in Biorelevant Bicarbonate Buffer Containing Sodium Chloride: Precipitation of Hemi-hydrochloride Salt at the Particle Surface. Pharm Res (2025). https://doi.org/10.1007/s11095-025-03905-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s11095-025-03905-4?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=oa_20250811&utm_content=10.1007%2Fs11095-025-03905-4
(オープンアクセスです)
まずはじめに、pH6.5, 10 mM BCB, I = 0.14 M (NaCl) (BCB-NaCl)における残存粒子をPXRDとDSCで分析しました。
すると、残存粒子は、従来知られていたトスフロキサシンフリー体2水和物(TFLX FF)とは一致しませんでした。
溶出試験液の組成を変えて残存粒子を測定すると、NaClを含まない場合は、TFLX FFが析出してくることが分かりました。
したがって、BCB-NaClで発見された新規結晶は、NaClが原因で生成されることが分かりました。
ここまでは、すんなりと研究は進みした。
しかし、この残存粒子は何なのか?
そこで、標準物質の別途合成に取り掛かりました。
まずは、TFLX TSの再結晶から始めました。(残存粒子が不純物の可能性もありますよね?)TFLX TSは、水だけでなく様々な溶媒に難溶でしたが、エタノール/水混液を用いた温度差法で、きれいに再結晶できました。(Figure 1)
次に、TFLX FFを作成しました。まず初めに、TFLX TSをエタノール/水混液加熱して溶かします。次に、中和等量のNaOHを加えると、TFLX FFがさっと析出します。
実は、このTFLX FFは、100%RHのチャンバーから取り出した直後は、約4水和物になっています(TG-DTA)。しかし、室内条件では速やかに2水和物になります。
したがって、水中では4水和物の可能性が高いです。
最後に、TFLX FFからTFLX塩酸塩を作成しました。TFLX FFも水だけでなく様々な溶媒に難溶でしたが、NaOH溶液には溶けます。
そこでまず、TFLX FFをNaOH溶液で完全に溶かします。
次に、1:1等量の塩酸を一気に加えます(NaOHのモル量を引いた後)。すると、結晶がさっと析出します。
PXRDからは、TFLX FFの残存は否定されました。したがって、塩酸塩結晶が析出したことになります。
この塩酸塩結晶も、水中では10水和物ですが、室内条件では速やかに0.5水和物になります。(これらの等量は化学量論比が分かった後に再計算したものです。)
この結晶のPXRDとDSCは、BCB-NaClにおける残存粒子と一致しました。
したがって、BCB-NaCl中では、pH 6.5であるにもかかわらず、塩酸塩結晶が析出しています。
電子顕微鏡などでの結果から、これは粒子表面析出であることがわかりました。
残る問題は、この塩酸塩結晶の化学量論比の同定です。
この時点で、我々は、TFLXの化学構造から、この塩酸塩結晶は、TFLX:HCl=1:1ではないかと考えていました。
理想は、単結晶構造解析ですが、塩酸塩結晶は調べた範囲では、すべての溶媒に不溶で、再結晶で大きな結晶を作ることはできませんでした。
また、水和数が不安定であるため元素分析も諦めました。
そこで、pH溶解度プロファイルを測定しました。pHはHClで調整しました。
すると、これまで全く見たことが無い、pH溶解度プロファイルが得られました。(Figure 7B)
このpH溶解度プロファイルは、1:1あるいは1:2では、全く説明できませんでした (TFLXは低い塩基性pKaを持っているので、低pH側では1:2の可能性もありました)。
ここで、我々の研究は、座礁に乗り上げてしまいました。
pH溶解度プロファイルを取り直したり、別途合成を繰り返したり、TFLXとH2Oの精密定量を試みたり(水和数が不安定で難しい)、、、いろいろしました。
もちろん、pH滴定も考えました。通常、pH滴定は溶液状態で行います。
しかし、上述のように、この塩酸塩結晶は溶媒に不溶です。
固体懸濁液では、平衡になるまでの時間がかかるのでpH滴定は大変なのです。
でも、最後の手段として、固体懸濁状態でのpH滴定を、学生にやってみてもらいました。
結果は、TFLXとHClの比は2:1であることを示していました。(Figure S3)
(対照として、TFLX TSのpH滴定もおこない、こちらは1:1となりました。)
これは、にわかには信じられない結果です。
この化学量論比(2:1)(Hemi)は、硫酸、フマル酸や、マレイン酸のように2価以上のカウンターイオンの場合はよく知られています。しかし、1価の塩酸でこのような化学量論比は、通常考えにくいのです。
そこで、TFLX:HCl=2:1の場合のpH溶解度プロファイルの理論式を考えてみました。
この化学量論比の場合、溶解度積は、Ksp = [TFLXH+][TFLX][Cl-]となります。
これを電荷中性の式に入れて解くことで、pH溶解度プロファイルが得られます(3次方程式なので、2分法で解いています)。
すると、pH溶解度プロファイルの実験データと完璧に一致しました。
さらに、念のため、本分野の大家であるAlex Avdeefさんにデータを送って、解析してもらったところ、TFLX:HCl=2:1で間違いないということでした。
Alex Avdeefさんも、「このようなpH溶解度プロファイルは初めて見た」と言っていました。
さて、ここまで来て、もう一度溶出試験の結果を見直してみました。
TFLX TSが解けてTFLX FFが固体として析出する場合、溶液中にトシル酸(R-SO3H)が放出されますので、緩衝能が低い溶液中では、溶出試験後のpHが下がります。
これは、実際にそうなります。(Table II)
一方、TFLX TSが解けてTFLX HCl(1:1)がとして析出する場合、トシル酸(R-SO3H)が放出されますが、同時にHClが取り込まれますので、溶出試験後のpHはそのままのはずです。
しかし、Table IIをよーーーく見てみると、塩酸塩結晶が析出している場合でも、溶出試験後のpHはやや下がっています。
これはなぜか???
Ksp = [TFLXH+][TFLX][Cl-]が析出する場合は、トシル酸が2分子放出され、塩酸が1分子取り込まれますので、差し引き1分子の酸が放出されます。
pHはこのことを教えてくれていたのです。
その後、他の薬物でヘミ塩酸塩がないかを文献検索したところ、2つだけ事例がありました。pH溶解度プロファイルは、今回の結果が初めての報告だと思います。
今回の結果は、非常に稀なケースと思われます。
In vivo予測の観点からは、これまで単にイオン強度や浸透圧の調整程度に考えられていたNaClが、実はこんなことを引き起こすことがあるというのが面白い点です。
これは、pH 6.5で起きています。塩酸酸性の低pH側では塩酸塩が析出する事例は多数ありますが、pH 6.5でこのような現象が起きることは、想定外でした。
製薬メーカの分析力であれば、最初の段階で組成を決定できたのかもしれません。しかし、残念ながら大学にはそのような装置はありません。
しかし結果として、ヘミ塩酸塩の驚くべき挙動に気付くことができたと思います。
[TFLXH+][TFLX][Cl-]は、塩なのか?共結晶なのか?面白いですね。